はじめに
「この性格、変えたほうがいんかな?・・・まぁでも「これが自分」ってことでええ気もするし・・・」
「俺はもっと社交的になりたい・・・のか? でも、無理しとる感じもしんどいし・・・」
「どこが諦めて受け入れるべきポイントなんやろか? 変わる努力って永遠に続けるべきなん?」
「才能か環境か」って一回は考えたことあるやん?
ていうか俺なんかは今だにグズグズ考えるんやけど。
どうしようもなった過去の40年間を、なんとか正当化したいっていうスケベ心が見え隠れしとるわけやけど(笑)。
もし「性格は変えられる」っていうなら変えたい。
けど、どうしようもないのにジタバタするのも苦しいだけ・・・。
まぁどうせ答えなんか出んのやろけど、それでも「なんとなく納得」くらいはしたいやん?
そんなわけで、“受容と変化の間”でフワフワしちゃってる俺とそこのあなた。
性格はどこまで変えられるのか/どこから受け入れるべきかを、サラサラっと考えてみたで。
行動に変えるためのちょっとしたワークやノート術とかも。
性格はどれくらい「生まれつき」で決まる?
それ系の本を読んでも、これまで人生の体感的にも、性格は40〜60%が遺伝で決まり、残りは環境や経験によって形づくられる、ってことでいんじゃねーかな。
ほぼ半々っていう、まぁなんとも退屈な数字というか結論(笑)。
例えば、俺自身が気になる性格傾向で言うと・・・
「人をどこまで信用するか(対人信頼性)」
「未来を楽観的に見るか悲観的に見るか(楽観性・悲観性)」
「リスクをどこまで取れるか(リスク許容度・冒険性)」
これらも、ほぼほぼ40〜60%の枠に収まるらしい。
でもここで面白いのは、後天的影響が大きいのが「非共有環境」(家庭環境の外)ってところ(兄弟でも違う体験)。
あとは「自己選択した行動」。
この辺は意外と興味深い。
結局性格は、「先天×後天」のかけ算ってことやね。
単に「俺はこういう人間だから」じゃなく、「この性質をどう使うか」がモテにも人生にも効いてくるってこと。
生まれつきの性格傾向は、イヤになるくらい間違いなくある。
でもそれをどう育て、どう活かし、どう変えていくかは、結構後天的要素が握ってたりする。
・・・ってまぁなんていうか、フツー(笑)。
☑ 一応、よく言われるビッグファイブで見ると・・・
・「外向性」&「神経症的傾向」:う〜ん、やや変えにくい
・「誠実性」&「協調性」&「開放性」:がんばれば割と変えやすい
それっぽくまとめると・・・
・「遺伝」で”基礎のクセ”が決まっちゃう(キレやすいとか、几帳面とか、ビビりとか)
・「家庭環境」よりも「非共有環境」でかなり味付けされる(出会いや体験が性格に深みを与える)
・「意志と習慣」で性格は進化も変化もできる!
って感じかな。
性格の「後天的変化」は、「神経回路とホルモンの”クセ”」の再形成
性格って、脳内の「よく使うパターン(神経回路)」の”クセ”のことらしいのね。
で、それって、ドーパミンとかセロトニンとかのホルモンバランスの影響が大きい。
言い換えると、「よく使う感情&よく取る行動が、その人らしさを形成する」って感じ。
⚫︎神経回路のクセ = 「脳内のよく使うパターン」
- たとえば、「失敗したら恥ずい〜・・・」って考えるクセがある人は・・・
→扁桃体(不安・恐怖)と前頭前野(自己制御)の連携がそのように配線されてる。 - でも逆に、「失敗ってのは学びなんじゃい!」と捉える人は・・・
→報酬系(側坐核)と快楽記憶(海馬)が強化されてる。
ちょいとムズい感じになったけど、要するに、性格は「脳の使い方」そのものってこと。
⚫︎ホルモンのクセ = 「感情のホルモンドリップ」
- 例えば:
- セロトニン不足 → 神経症傾向↑、不安・怒りが高まる
- ドーパミン多め → 開放性↑、冒険的・快楽志向
- オキシトシン↑ → 協調性↑、共感力・信頼感アップ
- コルチゾール↑ → 慢性ストレス→防衛的な性格に
→ホルモンってやつは、感情のフィルターとか潤滑油みたいな役割を果たしとるって考えたらイメージしやすいかな。
神経・ホルモンの「クセ」は変えられる!
「じゃあどうしたらええの?」ってことで、ちょっとイキってまとめてみた(笑)。
以下の6つが、現代科学で「性格再形成の手段」として”あり”とされとる。
| アプローチ | 働きかける場所 | 例 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ①認知行動療法(CBT) | 前頭前野(考えの枠組み) | 自動思考の書き換え | 脳の配線が変わる |
| ②瞑想・マインドフルネス | 扁桃体・島皮質・前帯状皮質 | 姿勢・呼吸・今に集中 | ストレス耐性アップ/EQ↑ |
| ③習慣化 | ドーパミン系/前頭葉 | 筋トレ・ジャーナル・アファメーション | 神経可塑性が発揮される |
| ④社会的つながり | オキシトシン系 | 信頼できる仲間/安全基地 | 安定感・協調性↑ |
| ⑤食事・腸内環境 | セロトニン系 | 発酵食品・食物繊維 | 精神安定・意欲↑ |
| ⑥音楽・芸術 | ドーパミン・快感系 | 演奏・創作・鑑賞 | 創造性↑・幸福感↑ |
自分を取り巻くあらゆるものに対して「なんで?どういうこと?」って突き詰める「問い直し(哲学)」とか。
ぼんやりした思考や感情を「言語化する」「視覚化する」とか。
あとはチャレンジ系の「とにかく行動する」ってのは、まさにこの性格再形成そのものかもな。
つまり日常ってやつは、過ごし方次第でちょっとずつ、自分の脳を書き換えてる最中とも言えそう。
「性格」は脳の“よく踏むあぜ道”みたいなもん。
でも新しいルートを見つけて、そこを選び続けたら、ちゃんと”獣道”ができる。
で、その獣道は、やがて自分にとっての”正道”、つまり“生き方”になる。
かっこよく言うとそんな感じ(笑)。
→ 脳は生涯を通じて変わり続ける。「性格は育てられるし、書き換えもできる」ってのが現代科学の結論
受容するか?変えるか? その境界線はどこ?
で、大事なんはこっから。
「この性格、いい意味で諦めて受け入れた方がええの?それとも知識と訓練で前向きに変えた方がええの?」
ここんところを自分でハッキリ自覚すんのムズいんのよね。
「あぁ、お母ちゃんの無条件の愛を感じていられたら、自分の性格に疑問を持つこともなかったかもなぁ」という幼いままの本音がチラホラ(笑)。
まぁそれは置いといて、境界線見極めのポイント。
5つほど考えてみた。
⚫︎【脳科学的視点】「”神経の可塑性”が効く領域か?」
→見極めポイント:「前向きに変えようとする努力が効いてる実感ある?」
⚫︎【心理学的視点】「自己効力感を持てる領域か?」
→見極めポイント:「変われる手応え・小さな成功体験、ある?」
⚫︎【感情的視点】「無理して変えようとして“しんどさ”が増してないか?」
→見極めポイント:「努力していて“希望”が湧く?、それとも“枯れていく”感じがする?」
⚫︎【動機的視点】「“変えたい”の根が自分由来か?」
→見極めポイント:「それ、誰に認められたいん?、自分の物差しになっとる?」
⚫︎【実存的視点】「そもそも“変える必要”あるんか?」
→見極めポイント:「“変えたい”じゃなくて、“認めてほしい”だけちゃう?」
どう?
自分で言うのもなんやけど、割と説得力あるんちゃうかな?
ただ、どれも「それが分からんから困っとんじゃい!」っていう気がしないでもないけど(笑) 。
まぁいずれにしても「やってみる」っていう”行動”は絶対。
あと、変わる変わらない以前に、「別に今の自分もOK」っていう自己受容も必須やろな。
その上で、「変えようとする苦しみが“未来へのチケット代”か、“自己否定の利息”かを見極めろ!」っちゅうこっちゃ。
⭕️ 変化の痛みが”成長痛”なら楽しんで前進!
❌ ”自己否定ループ”なら一度立ち止まれ!もしくは止めちまえ!
「変われることを信じる勇気」と「変えられないものを受け入れる静けさ」──
そして何より、「その違いを見極める叡智」こそが、俺らが目指す”性格”との付き合い方の”核”
「性格→行動」じゃなくて「行動→性格」で“逆再構築”する
例えば、よく啓発本に書いてあるのでいうと・・・
- なりたい性格を言語化
- 行動に分解(ミニタスク化)
- 続けられるフォームにする
- 成功体験を記録
- 忘れず「言語化」しながらデータ化
みたいな?
うん・・・まぁどれも間違いないんやろけど、なんかおもんない(笑)。
なので、俺の「行動→性格」の実体験を書いてみる。
1:筋トレ習慣
「ハイ出たお約束」って思ったん?
そのセリフはやってから言おう。
肉体が変わり、生活のリズムが変わり、食生活が変われば、性格は間違いなく変わる!
もうこれは100%!
もっと細かく書いてもええけど、これに関しては「やろう!」だけでいい。
2:情報の取捨選択
テレビは捨てる、ネットニュースは遮断する、SNSは見ない、くだらない人間関係は切る、家内を徹底的に断捨離する。
自分にとって必要な情報のみを厳選し、決意を持ってノイズを断つ!
自分にとって大事なものがクリアになって、なにより生きるのが楽になる。
そして必然、行動が最適化され、性格も変わる。
3:本音をぶちまける環境を確保する
肉親でも恋人でも、はたまた友人でもいい。
最近ならAI相手だっていい。
思ったことは躊躇も遠慮もなくドンドン言語化して吐き出す。
対話を惜しんではいかん。
するとあら不思議、思考も感情も整理されてフッと心が整う。
こういうセーフプレイスの確保とアウトプット習慣は、意外や意外、性格形成への影響は大。
俺の体感でしかないけど間違いなし!
「行動は性格を変える」は真実。
性格は、言ってみれば自分の愛すべき”キャラ”。
大事に大事に育てるものと思えばモチベにもなる☆
性格とモテの関係は?
こんなん今更いうことでもないけど、性格がいい方がそらモテるわなぁ(笑)。
心理学の世界で有名な既出の「ビッグ5」(外向・誠実・協調・開放・神経症)を元にサラッとまとめといたから見てみて。
たぶん「そらそうやろ」って感想しかないと思うけど(笑)、でも知ってるようで知らんってこともあるから、まぁサラッとね。
| モテ要素 | 関連性格因子 |
|---|---|
| 話しかけやすさ・いわゆるコミュ力 | 外向性(惹きつけ力)、開放性(会話力) |
| 言行一致の安心感・思いやりと優しさ | 誠実性(信頼)、協調性(癒し) |
| 知的センス(ストーリー・ギャップ・ユーモア) | 開放性(知性・色気) |
| 会話の波長(否定しない聞き上手) | 協調性(包容力)、外向性(他人への関心度) |
| 欠点や弱さから見える奥行きや余白の魅力 | 神経症的傾向(繊細さと大胆さのバランス) |
”モテ”においての”性格”とは、「にじみ出る人間的質感」の集大成
最後に:遺伝には逆らえんけど、性格の再構築は意外といけるという両面
どうかね?
性格は「遺伝的にどうしようもない。でも頑張ればなんとかなることもある」っていう、ものごっつありふれた結論やけど(笑)。
性格は「変えにくい部分」があるのは間違いない。
けどさ、なんにもせんとタメ息つくより、とりあえずやれることはやってみるってことでいんじゃね?
「まぁどうしようもねーよ」っていうオチかも知らんけど、そんなんも含めて、自分の可能性をおもろがってみるってことで。
まぁシンプルに「自分との対話」って意外と楽しいからね。
とりあえず「自分が思う自分の性格」とか「理想の性格」とかを言語化する、みたいなことからスタートすれば、意外と何歳からでも進化できるかもよ。
で、その進化は、誰かの期待に応えるためじゃなくて、「自分が、自分のことを好きになるため」。
なんつってな☆
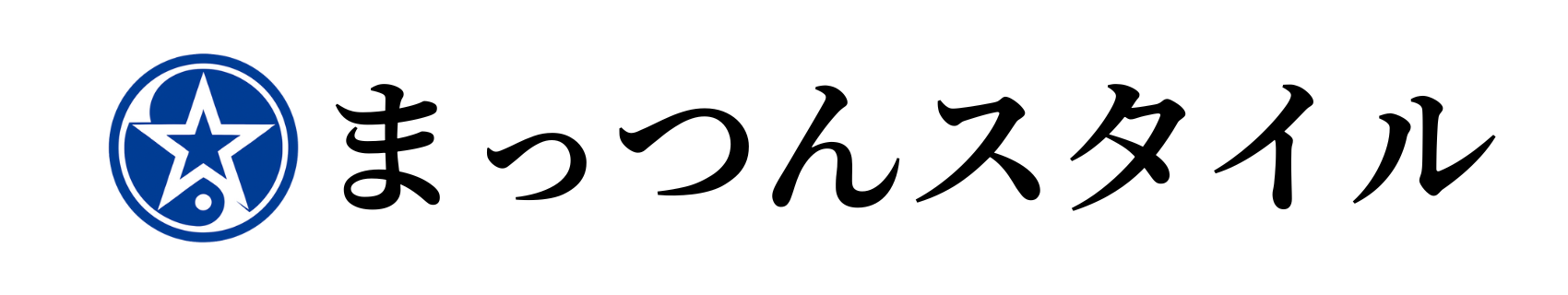



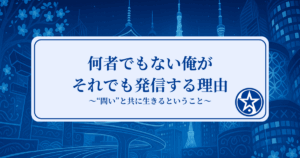
コメント